1.腎臓の構造と働き
●ナトリウムイオンが再吸収される主な部位はどれか。
1.近位尿細管
2.Henle<ヘンレ>のループ<係蹄>下行脚
3.Henle<ヘンレ>のループ<係蹄>上行脚
4.遠位尿細管
5.集合管
1
近位尿細管でナトリウムイオンは約80%再吸収される。
●腎臓について正しいのはどれか。
1.腹腔内にある。
2.左右の腎臓は同じ高さにある。
3.腎静脈は下大静脈に合流する。
4.腎動脈は腹腔動脈から分かれる。
3
腎静脈は下大静脈に合流する。1.腎臓は後腹膜臓器。2.右が少し下。
●蠕動運動がみられるのはどれか。2つ選べ。
1.腎動脈
2.腎盂
3.尿管
4.膀胱
5.尿道
2,3
●正常な糸球体で濾過される物質はどれか。
1.フィブリノゲン
2.ミオグロビン
3.アルブミン
4.血小板
5.赤血球
2
ミオグロビンは骨格筋や心筋に含まれる比較的小さい蛋白質なので濾過される。その他フィブリノゲンやアルブミンのような血漿蛋白質は大きいので濾過されない。血小板や赤血球などの血球も濾過されない。
●糸球体濾過量の推定に用いられる生体内物質はどれか。
1.尿素
2.イヌリン
3.ビリルビン
4.クレアチニン
5.パラアミノ馬尿酸
4
クレアチニンは糸球体濾過量の推定に用いられる。
●抗利尿ホルモン<ADH>について正しいのはどれか。
1.尿細管における水分の再吸収を抑制する。
2.血漿浸透圧によって分泌が調節される。
3.飲酒によって分泌が増加する。
4.下垂体前葉から分泌される。
2
抗利尿ホルモン<ADH>(バソプレシンともいう)は血漿浸透圧が上昇する(濃くなる)と、脳下垂後葉から分泌され、集合管で水分の再吸収の促進を行う。つまり、血液中の濃度を薄めようとする。
●抗利尿ホルモン<ADH>の分泌を抑制するのはどれか。
1.血圧低下
2.循環血漿量減少
3.血漿浸透圧低下
4.血中カルシウム値低下
3
抗利尿ホルモン<ADH>(バソプレシンともいう)は血漿浸透圧が上昇する(濃くなる)と、脳下垂後葉から分泌され、集合管で水分の再吸収の促進を行う。つまり、血液中の濃度を薄めようとする。なのでこの場合、分泌を抑制するのは血漿浸透圧の低下である。
●腎臓でナトリウムイオンの再吸収を促進するのはどれか。
1.バソプレシン
2.アルドステロン
3.レニン
4.心房性ナトリウム利尿ペプチド
2
アルドステロンは集合管でナトリウムイオンの再吸収を促進する。
●アンジオテンシンⅡの作用はどれか。
1.細動脈を収縮させる。
2.毛細血管を拡張させる。
3.レニン分泌を促進する。
4.アルドステロン分泌を抑制する。
1
アンジオテンシンⅡは細動脈を収縮させ血圧を上昇させる役割と、副腎皮質からアルドステロンの分泌を促進する。アルドステロンは集合管でナトリウムイオンの再吸収を促進する。
●アルドステロンで正しいのはどれか。
1.近位尿細管に作用する。
2.副腎髄質から分泌される。
3.ナトリウムの再吸収を促進する。
4.アンジオテンシンⅠによって分泌が促進される。
3
アルドステロンは集合管でナトリウムイオンの再吸収を促進する。
●尿量の調節に深く関わるホルモンはどれか。
1.ガストリン
2.カルシトニン
3.グルカゴン
4.ソマトスタチン
5.バソプレシン
5
抗利尿ホルモン<ADH>(バソプレシンともいう)は血漿浸透圧が上昇する(濃くなる)と、脳下垂後葉から分泌され、集合管で水分の再吸収の促進を行う。つまり、尿量を調節することで、血液中の濃度を薄めようとする。
2.腎臓の疾患
●腎機能障害のある患者にみられる浮腫の原因はどれか。
1.リンパ管閉塞
2.カリウム貯留
3.血管透過性亢進
4.血漿膠質浸透圧低下
4
膠質浸透圧とは血漿中に含まれる膠質、主にアルブミンという蛋白質が作り出す圧力のこと。腎機能低下などにより普段濾過されないアルブミンが濾過されてしまうと、血漿内からアルブミンが減少し、それによって膠質浸透圧も低下し、血管外に水分が漏れ出し浮腫の原因となる。
●腎前性腎不全が起こるのはどれか。
1.前立腺肥大症
2.急性心筋梗塞
3.急性尿細管壊死
4.急性糸球体腎炎
2
腎前性腎不全は急激に腎臓に入ってくる血液量が低下する。急性心筋梗塞では、心不全や心原性ショックによって腎血流量が急激に低下する。その他、脱水や大量出血でも起こる。
●慢性腎不全で正しいのはどれか。
1.高蛋白食が必要である。
2.高カルシウム血症となる。
3.最も多い原因は腎硬化症である。
4.糸球体濾過量<GFR>は正常である。
5.代謝性アシドーシスを起こしやすい。
5
尿(酸性)を捨てれないから代謝性アシドーシス。1.慢性腎不全では糸球体濾過量<GFR>が低下し、赤血球やタンパク質が尿に含まれて出てしまう。このような状態でさらにタンパク質を摂取すると腎臓に負担がかかるので低タンパク質食にする必要がある。2.慢性腎不全ではカリウムとリンは上昇し、カルシウムは低下する。3.糖尿病性腎症が最も多い。4.GFRは低下する。
●慢性腎臓病の説明で正しいのはどれか。
1.糖尿病腎症は含まれない。
2.病期分類の5期から蛋白制限が必要である。
3.腎障害を示す所見が1週間持続すれば診断できる。
4.糸球体濾過量<GFR>の低下は診断の必要条件である。
5.病期の進行とともに心血管疾患のリスクも高くなる。
5
腎臓が悪くなると心臓も悪くなり、心血管疾患のリスクが高くなる。2.ステージ3から蛋白制限がある。3.慢性腎臓病は腎障害を示す所見が3か月以上続く状態である。4.GFRは診断の必要条件ではない。
●慢性腎不全によって起こるのはどれか。2つ選べ。
1.低血圧
2.低リン血症
3.低カリウム血症
4.低カルシウム血症
5.代謝性アシドーシス
4,5
慢性腎不全ではクレアチニンやBUNやカリウムやリンは上昇し、GFRの値とカルシウムは低下する。また、尿(酸性)を捨てれないから代謝性アシドーシス。
●慢性腎不全で出現しやすいのはどれか。
1.羽ばたき振戦
2.眼球突出
3.ばち状指
4.出血傾向
4
慢性腎不全の末期では血小板の凝集能の低下、血小板粘着能の低下などが起き出血傾向となる。
●慢性腎臓病においてリンの代謝障害によって生じる症状はどれか。
1.骨痛
2.貧血
3.浮腫
4.不整脈
1
慢性腎臓病が続くとリンが腎臓で捨てれないので高リン血症となりカルシウムも作れなくなり低カルシウム血症となる。低カルシウム状態になると副甲状腺が、足りないカルシウムを骨から取り出して補おうとするので、骨が一気にぼろぼろになる。つまり副甲状腺機能亢進症によって骨粗鬆症がすすむ。当然1の骨痛が生じる。
●腎臓疾患患者の食事療法で正しいのはどれか。
1.浮腫、乏尿および高血圧がある場合は脂質を制限する。
2.慢性腎不全の代償性多尿期ではナトリウム制限はない。
3.血中の尿素窒素値が上昇している場合はカルシウムを制限する。
4.急性腎不全の乏尿期の水分摂取量は前日の尿量+500mL以内とする。
4
●Aさん(76歳、女性)は、ステージ2の慢性腎臓病と診断された。身長146cm、体重50kg。日常生活は自立し、毎日家事をしている。週2回、ビールをグラス1杯程度飲んでいる。
Aさんへの生活指導の内容で優先されるのはどれか。
1.安静
2.禁酒
3.減塩
4.体重の減量
3
慢性腎臓病では塩分制限(6g)、低蛋白質食、カリウム・リンが制限される。
●慢性腎不全で透析導入を判断するときの指標となる検査はどれか。
1.尿酸<UA>値
2.糸球体濾過量<GFR>
3.点滴静注腎盂造影<DIP>
4.PSP<フェノールスルホンフタレイン>15分値
2
透析導入は糸球体濾過量GFRの値で判断される。15mL/分以下になると透析導入。
●慢性腎不全で透析導入を判断するときの指標となる腎機能検査はどれか。
1.PSP(フェノールスルホンフタレイン)15分値
2.糸球体濾過量(GFR)
3.点滴静注腎盂造影(DIP)
4.逆行性腎盂造影(RP)
2
透析導入は糸球体濾過量GFRの値で判断される。15mL/分以下になると透析導入。
●透析導入患者の原疾患として最も多いのはどれか。
1.慢性糸球体腎炎
2.多発性嚢胞腎
3.ループス腎炎
4.糖尿病腎症
5.腎硬化症
4
透析を始める原疾患は糖尿病性腎症が最も多い。
●血液透析の導入期の看護で適切なのはどれか。
1.飲水は制限しない。
2.不均衡症候群に注意する。
3.透析実施中の歩行を促す。
4.血圧はシャント肢で測定する。
2
血液透析では、細胞外の老廃物は除去され細胞内には老廃物がたまるという状態が起こり、細胞内と細胞外の浸透圧の不均衡が生じることがあり、これを不均衡症候群という。不均衡症候群が生じると細胞外から細胞内へ水が移動し、細胞自身に浮腫が起こる。これが脳で起こると脳浮腫となり頭蓋内圧亢進症状が現れる。症状は頭痛・悪心・嘔吐・筋けいれん・意識障害などである。不均衡症候群はまだ体が透析に慣れていない導入期に起こる。
●維持血液透析中の看護で適切なのはどれか。
1.シャント肢を抑制する。
2.室温を18℃に設定する。
3.筋肉のけいれんの出現に注意する。
4.患者が吐き気を感じたら座位にする。
3
血液透析では、細胞外の老廃物は除去され細胞内には老廃物がたまるという状態が起こり、細胞内と細胞外の浸透圧の不均衡が生じることがあり、これを不均衡症候群という。不均衡症候群が生じると細胞外から細胞内へ水が移動し、細胞自身に浮腫が起こる。これが脳で起こると脳浮腫となり頭蓋内圧亢進症状が現れる。症状は頭痛・悪心・嘔吐・筋けいれん・意識障害などである。4.吐き気の出現は不均衡症候群の症状なので注意する必要があるが座位にする必要はない。
●血液透析を受けている患者への食事指導で適切なのはどれか。
1.乳製品の摂取を勧める。
2.レバーの摂取を勧める。
3.穀物の摂取を制限する。
4.生野菜の摂取を制限する。
4
Kがたまると不整脈を起こすので制限する。(生野菜・果物・コーヒーなど)。Pがたまると骨がぼろぼろになるので制限する。(蛋白質・卵黄・レバー・ピーナッツ・チーズなど)
●血液透析について正しいのはどれか。
1.合併症は腹膜炎が多い。
2.食事はカルシウムを制限する。
3.導入初期には不均衡症候群が起こる。
4.導入の原因疾患はIgA腎症が最も多い。
5.透析に用いる半透膜はタンパク質が通過する。
3
導入期には不均衡症候群が起こりやすい。1.合併症は不均衡症候群。2.カリウム・リン・塩・タンパク質の制限がある。4.糖尿病性腎症が最も多い。5.水・電解質・尿素などは透過しやすく、タンパク質は透過しにくい。
●血液透析と比較した連続携行式腹膜灌流法(CAPD)の特徴はどれか。
1.カリウム制限が厳しい。
2.シャント造設が必要ない。
3.週あたりの透析回数が少ない。
4.不均衡症候群が出現しやすい。
2
腹膜透析は自身の腹膜を利用して血液中の老廃物を除去する。シャントがいらず、腹腔内にカテーテルを入れて透析液(グルコース入り)を注入し腹膜で仕分けされた老廃物を取り出す。月1回通院し、1日4回自身で透析液を交換する必要がある。交換に至っては清潔な環境で窓や扉は閉めて冷暖房もOFFにして行う。合併症の腹膜炎に注意する必要がありカテーテル出口部のケアや腹痛・排液のにごりが無いか注意する。食事制限は水・塩は×、低エネルギー食が良い。このようにして行う腹膜透析は仕事や旅行、入浴もできるので働き盛りの人には都合が良いが、ずっとはできず5年をめどに血液透析に移行していく。
●連続携行式腹膜灌流法(CAPD)で最も適切なのはどれか。
1.入浴はできない。
2.スポーツは制限なく行える。
3.低エネルギー食にする必要がある。
4.バッグ交換は通気のよい場所で行う。
3
腹膜透析の透析液にはもともとグルコースが含まれているため、エネルギーが過剰にならないようにするため低エネルギー食にする必要がある。腹膜透析は自身の腹膜を利用して血液中の老廃物を除去する。シャントがいらず、腹腔内にカテーテルを入れて透析液(グルコース入り)を注入し腹膜で仕分けされた老廃物を取り出す。月1回通院し、1日4回自身で透析液を交換する必要がある。交換に至っては清潔な環境で窓や扉は閉めて冷暖房もOFFにして行う。合併症の腹膜炎に注意する必要がありカテーテル出口部のケアや腹痛・排液のにごりが無いか注意する。食事制限は水・塩は×、低エネルギー食が良い。このようにして行う腹膜透析は仕事や旅行、入浴もできるので働き盛りの人には都合が良いが、ずっとはできず5年をめどに血液透析に移行していく。
●経皮的腎生検を受ける患者への説明で適切なのはどれか。
1.検査中の体位は仰臥位とする。
2.穿刺時に繰り返し深呼吸をする。
3.検査後はベッド上安静とする。
4.検査後2日間は禁食にする。
3
腎生検は腹臥位で行う。息をすると腎臓の位置が動くので30秒ほど息を止める。検査後は6時間は仰臥位で安静、その後1日ベッド上安静。血尿に注意し、1か月程度は激しい運動は控える。
●次の文章を読み問題1~3に答えよ。
34歳の男性。運送会社で配達をしている。6か月前の職場の健康診断で、血圧142/90mmHg、尿蛋白(2+)を指摘されたが放置していた。1週前、風邪症状の後に紅茶色の尿がみられたため内科を受診した。血清IgAが高値のため検査が必要となり入院した。
問題1.経皮的腎生検を行うことになった。
説明で適切なのはどれか。
1.「左右交互に横向きになって両方の腎臓に針を刺します」
2.「針を刺すときは深呼吸を繰り返してください」
3.「検査2時間後に止血が確認できたら歩いてかまいません」
4.「検査後2週間は重い物を運ぶ仕事は控えてください」
4
検査後6時間は仰臥位で安静、その後1日はベッド上安静、血尿に注意し、1か月程度は激しい運動は避ける。1.腹臥位で刺すのは片側のみ。2.息をすると腎臓の位置が動くので30秒ほど呼吸を止める。
問題2.検査の結果、IgA腎症と診断され昼間だけの勤務に変更した。塩分1日7g以下の食事制限と3か月ごとの定期受診が指示された。塩辛いものが好物で外食の多い患者は「塩気がなくて食べた気がしない」と減塩食に物足りなさを感じている。
対応で適切なのはどれか。
1.「酸味や香味を利用するとよいでしょう」
2.「各食事で均等に食塩を摂取しましょう」
3.「市販のレトルト食品は塩分が少ないので活用するとよいです」
4.「料理は人肌程度の温度にすると塩味をよく感じることができます」
1
塩分を増やさずに味を感じるには酸味や香味を利用すると良い。3.レトルト食品は塩分が多い。4.確かに温度が下がると塩分を感じやすくなるが、人肌程度ではあまり変化なし。
問題3.仕事が忙しくなり、退院後は一度も受診をせずに2年が経過した。2か月前から疲れやすくなったが、仕事のせいだと思い放置していた。1週前から息切れ、食欲不振および浮腫が出現し、昨日から眠気と嘔気および嘔吐とがあり外来を受診した。体温36.5℃。脈拍数98/分。血圧238/112mmHg。血液検査で尿素窒素100mg/dL、クレアチニン12.0mg/dL、Hb7.1g/dL。胸部エックス線写真で心拡大と肺うっ血とが認められ入院した。
直ちに行われるのはどれか。
1.輸血
2.血液透析
3.利尿薬の内服
4.胸腔ドレナージ
2
血圧も高く、クレアチニンの基準値1や尿素窒素BUNの基準値8~20からも外れて上昇していたり心不全症状があることから尿毒症が起こっていると考えられるので血液透析が必要である。
●次の文章を読み問題1~3に答えよ。
Aさん(52歳、男性)は、5年前に健康診断で高血圧を指摘されていましたが、そのままにしていた。5年ぶりに健康診断を受けたところ尿蛋白+で、内科を受診し腎機能障害を指摘された。Aさんは、身長160cm、体重56kgであり、体温36.1℃、呼吸数18/分、脈拍64/分、整で、血圧166/96mmHgであった。血液検査データは、Hb9.3g/dL、アルブミン3.6g/dL、クレアチニン2.3mg/dL、HbA1c5.6%、K3.9mEq/L、推算糸球体濾過量<eGFR>25mL/分1.73㎡であり、特に自覚症状はなく、浮腫はみられない。
問題1.腎機能の悪化によると考えられるデータはどれか。
1.体重
2.血清カリウム値
3.ヘモグロビン値
4.血清アルブミン値
3
ヘモグロビン基準値は成人男性13.5~17.5g/dL、成人女性12~15.5g/dL。腎臓の機能の低下により、エリスロポエチン(骨髄に作用して赤血球を増加させるホルモン)が腎臓で作れないので貧血になる。
問題2.Aさんは、慢性腎臓病ステージ4と診断され、精査目的で入院した。「特に症状がないのに腎臓が悪いと言われて本当に驚いたよ。高血圧が関係していると医師に言われたけれど、どういうことですか」とAさんが看護師に尋ねた。
Aさんへの説明で適切なのはどれか。
1.「高血圧で尿が少なくなり腎臓を悪くします」
2.「高血圧が続くと腎臓の濾過機能が低下します」
3.「高血圧では腎臓病の症状が現れにくくなります」
4.「腎臓の機能がさらに低下すると血圧は低くなります」
2
高血圧で腎臓の血管に動脈硬化が起き、糸球体での濾過機能が低下し、腎機能が低下する。
問題3.現時点でAさんに起こる危険性が高いのはどれか。
1.低リン血症
2.血糖値の上昇
3.虚血性心疾患
4.甲状腺機能亢進症
3
Aさんの腎不全は高血圧によるものであるので、心臓も動脈硬化を起こしている可能性が高く、虚血性心疾患の危険性がある。
●次の文章を読み問題1~3に答えよ。
Aさん(34歳、男性)は、運送会社で配達を担当している。6か月前の職場の健康診断で、血圧142/90mmHgと尿蛋白2+、尿潜血2+を指摘されたが放置していた。1週前、感冒様症状の後に紅茶色の尿がみられたため内科を受診した。血清IgAが高値でIgA腎症が疑われ入院した。
問題1.確定診断のために必要な検査はどれか。
1.腎生検
2.尿細胞診
3.腎血管造影
4.腹部超音波検査
5.腎シンチグラフィ
1
IgA腎症の検査に腎生検がある。
問題2.AさんはIgA腎症と診断され、塩分1日6gの減塩食が開始された。入院前は塩辛いものが好物で外食が多かったAさんは「味が薄くて食べた気がしない。退院後も続けられるかな」と話している。
このときの対応で最も適切なのはどれか。
1.「つらいですが慣れてきます」
2.「最初に甘いものを食べてください」
3.「各食事で均等に塩分を摂取しましょう」
4.「酸味や香味を利用するとよいでしょう」
5.「市販のレトルト食品は塩分が少ないので活用するとよいです」
4
塩分を増やさずに味を感じるには酸味や香味を利用すると良い。5.レトルト食品は塩分が多い。
問題3.Aさんは退院後、仕事が忙しくなり一度も受診をせずに2年が経過した。2か月前から疲れやすくなったが、仕事のせいだと思い放置していた。1週前から息切れ、食欲不振および浮腫があり、昨日から眠気、悪心および嘔吐が出現したため外来を受診した。体温36.5℃。脈拍数98/分、血圧238/112mmHgであった。血液検査データは、尿素窒素100mg/dL、クレアチニン12.0mg/dL、Hb7.1g/dL。胸部エックス線写真で心拡大と肺うっ血とが認められ入院した。
直ちに行われるのはどれか。2つ選べ。
1.輸血
2.血液透析
3.利尿薬の内服
4.胸腔ドレナージ
5.降圧薬の点滴静脈内注射
2,5
クレアチニンの基準値1や尿素窒素BUNの基準値8~20からも外れて上昇していたり心不全症状があることから尿毒症が起こっていると考えられるので血液透析が必要である。また、血圧も非常に高いので降圧薬を投与する必要がある。
●次の文章を読み問題1~3に答えよ。
Aさん(50歳、男性、会社員)は妻と高校生の息子との3人暮らし。仕事を生きがいに働き続けてきた。慢性腎不全のため透析治療が必要になったが、本人の希望で連続携行式腹膜灌流法<CAPD>を導入することになり入院した。Aさんはこれからの生活がどのようになるのかを看護師に質問した。
問題1.Aさんに対する説明として正しいのはどれか。
1.「食事療法が必要です」
2.「通院は週に2,3回必要です」
3.「宿泊を伴う旅行はできません」
4.「カテーテル挿入術後の翌日から入浴できます」
1
血液透析に比べCAPDの方が食事制限はまだましだが、制限が一切ないわけではなく、塩・リン・タンパク質の制限はあり。カリウムの制限はない。2.通院は月1回。3.宿泊と伴う旅行ができる。4.入浴は感染予防のためしばらく(4,5か月程度)はできない。術後しばらくしてからシャワー浴が行える。
問題2.Aさんはできるだけ早い職場復帰を望んでおり、入院中はCAPDの操作に熱心に取り組んでいた。退院後、CAPDを1日4回(0時、6時、12時、18時)行うことになった。
Aさんが会社の昼休みにCAPDを行うために必要な設備はどれか。2つ選べ。
1.透析液を保管する冷蔵庫
2.透析液を温める電子レンジ
3.透析液の交換時に使用する個室
4.CAPDの物品を保管する専用棚
5.透析液の貯留中に使用するベッド
3,4
透析液交換時は清潔な環境で窓や扉は閉めて冷暖房もOFFにして行う、透析液は直射日光に当たらないよう注意する。交換後はカテーテル出口部のケアを行う(腹痛や排液のにごりに注意する→腹膜炎のおそれ)。
問題3.Aさんは「主治医からCAPDの合併症に腹膜炎があると聞きました。腹膜炎に早く気付くにはどうすればよいですか」と看護師に質問した。
Aさんに指導する観察項目はどれか。2つ選べ。
1.腹痛
2.体重の増加
3.腹部の張り
4.下肢のむくみ
5.透析液の排液のにごり
1,5
透析液交換後はカテーテル出口部のケアを行う(腹痛や排液のにごりに注意する→腹膜炎のおそれ)。
●次の文章を読み問題1~3に答えよ。
Aさん(47歳、男性、会社員)は妻と2人暮らしで、自宅の室内で犬を飼っている。15年前に慢性糸球体腎炎と診断され、徐々に腎機能低下が認められたので、2年前から慢性腎不全のため血液透析療法を週3回受けている。今回、弟から腎臓の提供の申し出があり、生体腎移植の目的で入院した。入院3日、Aさんの生体腎移植手術は予定通り終了した。
問題1.Aさんの手術直後に観察すべき項目で優先度が高いのはどれか。
1.尿量
2.血糖値
3.白血球数
4.シャント音
1
腎移植後の合併症は拒絶反応や、腎動脈血栓症、急性尿細管壊死などがあるため、尿量の観察は大切である。
問題2.Aさんは術前からタクロリムスなど複数の免疫抑制薬を服用している。Aさんは「移植したら免疫抑制薬を飲む必要があることは分かっているのですが、退院後は何に気を付ければよいですか」と看護師に質問した。
Aさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。
1.「犬は今まで通り室内で飼育できます」
2.「グレープフルーツは摂取しないでください」
3.「感染予防のため風疹のワクチン接種をしてください」
4.「薬を飲み忘れたときは2回分をまとめて服用してください」
2
タクロリムス(免疫抑制薬)を服用する際はグレープフルーツを摂取するとダメ。薬の血中濃度が上昇してしまい腎機能障害などの副作用が出ることがあるため。1.タクロリムス服用中で免疫を抑制中なので犬からの感染リスクがあるため注意が必要。3.タクロリムスと生ワクチンの併用は禁忌である。風疹のワクチンは生ワクチン。
問題3.Aさんは順調に回復し、移植後の拒絶反応もなく退院することになった。Aさんは「腎臓が悪くなってから気を付けないといけないことが多かったのですが、移植してこれまでの制約がなくなりますね」と話した。
Aさんの退院後の生活で継続が必要なのはどれか。
1.蛋白質の摂取制限
2.週3回の通院
3.水分の制限
4.体重の管理
4
腎移植後の体重の増加は腎臓に負担がかかり、移植後の腎臓の寿命を縮めてしまうことにつながるので体重の管理を行う。
3.膀胱・前立腺・泌尿器
●膀胱で正しいのはどれか。
1.漿膜で覆われている。
2.直腸の後方に存在する。
3.粘膜は移行上皮である。
4.筋層は2層構造である。
3
膀胱は3層構造になっており、内側から粘膜(移行上皮)→筋層(排尿筋・膀胱平滑筋)→脂肪層。1.一部だけ漿膜。2.膀胱は直腸の前。(普通に考えてケツの穴より前)
●排尿時に収縮するのはどれか。
1.尿管
2.尿道
3.膀胱平滑筋
4.内尿道括約筋
5.外尿道括約筋
3
膀胱平滑筋(排尿筋ともいう)は排尿反射の際に収縮する。1.2.4.5.が排尿時に収縮すると考えると結構拷問レベル
●膀胱の蓄尿と排尿反射で正しいのはどれか。
1.排尿中枢はホルモンによって制御される。
2.排尿反射は交感神経を介して起こる。
3.蓄尿時に内尿道括約筋は収縮する。
4.排尿時に外尿道括約筋は収縮する。
5.蓄尿時に排尿筋は収縮する。
3
内尿道括約筋や外尿道括約筋が弛緩(ゆるむ)しているとおしっこが出ちゃう。膀胱にためる時は収縮しているはず。
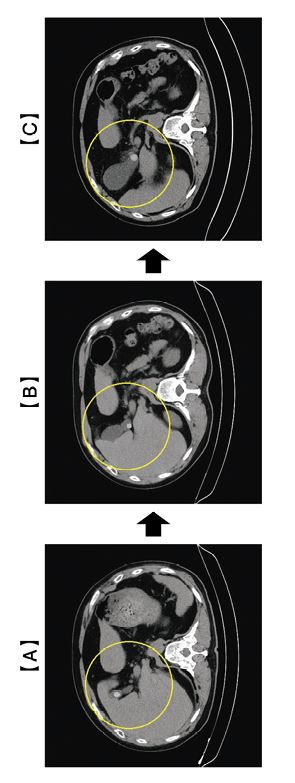
●膀胱癌について正しいのはどれか。
1.女性に多い。
2.尿路上皮癌より腺癌が多い。
3.経尿道的生検によって治療法を決定する。
4.表在性の癌に対して膀胱全摘除術が行われる。
3
1.50代以上の男性に好発。2.大部分が尿路上皮癌(移行上皮癌)である。
●膀胱癌のため尿路ストーマを造設する予定の患者への説明で適切なのはどれか。
1.「尿道の一部を体外に出して排泄口を造ります」
2.「尿意を感じたらトイレで尿を捨てます」
3.「ストーマの装具は毎日張り替えます」
4.「ストーマに装具を付けて入浴します」
5.「水分の摂りすぎに注意が必要です」
4
入浴時はストーマに装具を付けて入浴する。2.尿路ストーマでは尿意を感じない。
●Aさん(63歳、男性)。BMI24。前立腺肥大症のため経尿道的前立腺切除術を受け、手術後3日で膀胱留置カテーテルが抜去された。数日後に退院する予定である。
Aさんへの退院指導で適切なのはどれか。2つ選べ。
1.散歩を控える。
2.水分摂取を促す。
3.長時間の座位を控える。
4.時間をかけて入浴する。
5.排便時に強くいきまないようにする。
2,5
菌への感染防止に水分を積極的に摂取し、排尿を促す。排便時にいきむと血圧が上昇し、出血するリスクがある。
●Aさん(47歳、男性、会社員)は、痛風の既往があり、ほぼ毎日、飲酒を伴う外食をしている。1週間前に尿管結石による疝痛発作があり、体外衝撃波石破砕術<ESWL>を受けた。その結果、排出された結石は尿酸結石であることが分かった。
Aさんへの結石の再発予防に対する生活指導で適切なのはどれか。
1.「飲酒量に制限はありません」
2.「負荷の大きい運動をしましょう」
3.「1日2L程度の水分摂取をしましょう」
4.「動物性蛋白質を多く含む食品を摂取しましょう」
3
尿酸血症を改善するためには水分の十分な摂取が必要である。
●前立腺肥大症で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.進行すると水腎症となる。
2.外科治療は経尿道的前立腺切除術を行う。
3.直腸診で石の様な硬さの前立腺を触知する。
4.前立腺を縮小させるために男性ホルモン薬を用いる。
5.前立腺特異抗原<prostate specific antigen : PSA>値が100ng/mL以上となる。
1,2
前立腺肥大症では前立腺が肥大して尿閉が生じると水腎症となる。
●前立腺肥大症患者の頻尿の原因はどれか。
1.多尿
2.残尿量の増加
3.膀胱刺激症状
4.器質的膀胱容量の減少
2
●前立腺癌について正しいのはどれか。
1.肺転移の頻度は低い。
2.血清PSA値が高値となる。
3.患者の多くは60歳未満である。
4.テストステロン補充療法が行われる。
2
PSA高値は前立腺癌の診断基準にある。1.骨への転移や肺への転移が特徴。4.テストステロンは男性ホルモンであり、誤り。男性ホルモンを抑える。
●前立腺癌について正しいのはどれか。
1.骨への転移は稀(まれ)である。
2.血清PSA値が上昇する。
3.内分泌療法は無効である。
4.α交感神経遮断薬が有効である。
2
PSA高値は前立腺癌の診断基準にある。1.骨への転移や肺への転移が特徴。3.内分泌療法(ホルモン療法)は前立腺癌に有効である。男性ホルモンを抑える。
●前立腺癌で前立腺全摘出術後に起こりやすいのはどれか。
1.跛行
2.尿失禁
3.女性化乳房
4.排便回数の増加
2
前立腺全摘出術の合併症に尿失禁、性機能障害、尿道狭窄などがある。
●膀胱鏡検査で適切なのはどれか。
1.ファウラー位で行う。
2.全身麻酔下で行う。
3.無菌操作で行う。
4.検査後は水分摂取を控える。
3
膀胱鏡検査は無菌操作で行う。1.砕石位で。2.局所麻酔。4.尿路感染を防ぐため水分を積極的に摂取して尿で洗い流す。
●Aさん(42歳、男性)は、血尿を主訴に泌尿器科を受診した。診察の結果、Aさんは膀胱鏡検査を受けることになった。
Aさんへの検査についての説明で適切なのはどれか。
1.「入院が必要です」
2.「前日は夕食を食べないでください」
3.「局所麻酔で行います」
4.「終了後は水分の摂取を控えてください」
3
膀胱鏡検査は局所麻酔で行う。2.検査前日の夕食は食べても大丈夫。4.尿路感染を防ぐため水分を積極的に摂取して尿で洗い流す。
●膀胱鏡による組織検査を受ける成人男性への説明で正しいのはどれか。
1.「検査前は膀胱に尿をためてください」
2.「尿道から内視鏡を挿入します」
3.「膀胱に二酸化炭素を注入します」
4.「検査後24時間はベッドで安静にします」
2
膀胱鏡は尿道から挿入する。1.検査前に排尿を済ませておく。4.検査後は安静でなくて良い。
●経尿道的前立腺切除術後1日の患者。尿流出は順調であるにも関わらず「尿が出ない」と膀胱留置カテーテルの違和感を強く訴えた。
対応で適切なのはどれか。
1.鎮痛薬を使用する。
2.持続膀胱洗浄の速度を速める。
3.膀胱留置カテーテルを抜去する。
4.細い膀胱留置カテーテルに入れ替える。
1
実際には尿は出ていると記述がある。カテーテルへの違和感を感じているが、カテーテルは抜くことはできないので鎮痛薬を使用し、違和感を軽減する。
●Aさん(59歳、男性)は、経尿道的前立腺切除術後1日で、強い尿意を訴えているが腹部超音波検査で膀胱に尿は貯留していない。Aさんは、体温36.9℃、脈拍88/分、血圧128/86mmHgであった。尿は淡血性で混濁はなく蓄尿バッグ内に3時間で350mL貯留している。
この状態で考えられるのはどれか。
1.尿道狭窄
2.尿路感染症
3.膀胱刺激症状
4.膀胱タンポナーデ
3
術後に実際に膀胱に尿はたまっていないのに尿意を訴える→膀胱刺激症状。
●腎盂腎炎について正しいのはどれか。
1.両腎性である。
2.初尿を用いて細菌培養を行う。
3.肋骨脊柱角の叩打痛が特徴である。
4.原因菌はGram<グラム>陽性球菌が多い。
3
腎盂腎炎は女性に多く、グラム陰性桿菌が原因であり、下から上へと感染が拡がっていく上行感染である。症状は発熱・腰背部痛・CVA叩打痛。尿検査では中間尿をみる。治療は抗菌薬を使用し、水分を積極的に摂取し尿で菌を流す。
●成人の急性腎盂腎炎で正しいのはどれか。
1.男性に多い。
2.両腎性が多い。
3.初尿を用いて細菌培養を行う。
4.原因菌はGram<グラム>陰性桿菌が多い。
4
腎盂腎炎は女性に多く、グラム陰性桿菌が原因であり、下から上へと感染が拡がっていく上行感染である。症状は発熱・腰背部痛・CVA叩打痛。尿検査では中間尿をみる。治療は抗菌薬を使用し、水分を積極的に摂取し尿で菌を流す。
●Aさん(52歳、女性)は、子宮頸癌で広汎子宮全摘術後に排尿障害を発症した。退院に向けて自己導尿の練習を開始したが、39.0℃の発熱と右背部の叩打痛が出現した。
Aさんの症状の原因として考えられるのはどれか。
1.膀胱炎
2.虫垂炎
3.腎盂腎炎
4.骨盤内膿瘍
3
発熱や背部の叩打痛などの情報から腎盂腎炎であると考えられる。
●尿管結石症の治療で適切なのはどれか。2つ選べ。
1.尿路変更術
2.血管拡張薬の投与
3.カルシウム製剤の投与
4.体外衝撃波砕石術<ESWL>
5.非ステロイド系抗炎症薬の投与
4,5
尿路結石の痛みを軽減するために非ステロイド系抗炎症薬を投与する。
●Aさん(47歳、男性、会社員)は、尿管結石による疝痛発作で入院した。入院翌日、自然に排石され、疼痛は消失したものの、結石が残存している。入院前は、ほぼ毎日、飲酒を伴う外食をしていた。
Aさんへの退院指導で適切なのはどれか。
1.「シュウ酸を多く含む食品を摂取しましょう」
2.「1日2L程度の水分を摂取しましょう」
3.「排石までは安静にしましょう」
4.「飲酒量に制限はありません」
2
水分をしっかりと摂取して結石ができるのを防ぐ。
●勃起障害を起こすのはどれか。
1.糖尿病
2.高血圧症
3.甲状腺機能亢進症
4.胆石症
1
●次の文章を読み問題1~3に答えよ。
Aさん(56歳、男性)は、若いころテニスの選手で、現在も趣味でテニスを続けている。膀胱癌と診断され、膀胱全摘除術・回腸導管造設術の手術目的で入院した。Aさんは「外来で病名を聞いたときは動揺しましたが、家族と話し合い、今は心の準備ができています」と看護師に話した。
問題1.手術までの観察項目で緊急の処置を必要とする可能性があるのはどれか。
1.尿閉
2.頻尿
3.潜血尿
4.排尿時痛
1
尿閉は尿を排出できない状態なので緊急の処置が必要である。
問題2.術後5日、順調に回復しているAさんのストーマの色はどれか。
1.白色~淡黄色
2.黄土色~茶色
3.桃色~鮮紅色
4.灰色~黒色
3
問題3.看護師は、Aさんから「退院後はどのように生活が変わりますか」と質問された。
看護師の説明で適切なのはどれか。
1.「入浴の際、浴槽の湯に入ることはできません」
2.「食事の内容を変える必要はありません」
3.「排尿のときは導尿が必要です」
4.「テニスはできなくなります」
2
便のストーマは食事内容を考慮する必要があるが、尿路ストーマでは食事の内容を変える必要はない。1.浴槽には装具を装着して入れる。
●次の文章を読み問題1~3に答えよ。
Aさん、62歳の男性。印刷工場で長年働いている。最近、肉眼的血尿が出現し泌尿器科を受診した。診察の結果、入院し精密検査を受けることになった。
問題1.硬膜外麻酔下で膀胱鏡による膀胱組織の生検が予定された。
最も確認する必要があるのはどれか。
1.検査前の絶飲食
2.検査中の下肢のしびれ
3.検査直後の眠気
4.検査直後の血尿の増強
4
生検後は血尿が生じることがあるが、血尿の増強は出血の増加の可能性があるので確認する必要がある。1.検査前の絶飲食は不要。2.麻酔をしているためしびれ等は発生する。3.眠気は生じない。
問題2.膀胱癌と診断され、膀胱全摘術と回腸導管造設による尿路変更術が行われることになった。
術後の生活に関する説明で適切なのはどれか。
1.「尿意は残ります」
2.「尿の出口が二つになります」
3.「自己導尿が必要となります」
4.「パウチの装着が必要となります」
4
尿を貯留するための袋、パウチが必要である。1.尿意は生じない。2.尿はストーマからしか出ない。3.尿はストーマから出るので自己導尿は必要ない。
問題3.退院2週後の朝、Aさんから「昨夜から39.5℃の熱が続き、だるくて腰も痛い。食欲もないし、水も飲む気にならない」と泌尿器科外来に電話があった。
確認する情報で優先度が最も高いのはどれか。
1.咽頭痛の有無
2.排ガスの有無
3.排尿の量と性状
4.脈拍数とリズム
3
排尿の量や性状は尿路感染症を確認する上で優先度が高い。
●次の文章を読み問題1~3に答えよ。
Aさん(57歳、男性)は、芳香族アミンを扱う化学工場に39年勤務している。
現病歴:ここ数カ月で次第に尿の色が濃くなった。いきまないと排尿できなくなり、泌尿器科を受診し、採血および尿検査を受けた。
既往歴:特記すべき点なし。
生活歴:喫煙40本/日を36年間、焼酎120mLの飲酒をほぼ毎日、20年間続けている。
身体所見:顔面、四肢に浮腫なし、黒色便なし、血便なし。
検査所見:赤血球308万/μL、Hb9.9g/dL、血清アルブミン4.2g/dL、血清総ビリルビン0.2mg/dL、血糖102mg/dL、ヘモグロビンA1c<HbA1c>5.4%。
問題1.Aさんの尿所見で予測されるのはどれか。
1.蛋白尿
2.尿糖陽性
3.肉眼的血尿
4.ビリルビン尿
3
肉眼的血尿は膀胱癌の初期症状である。1.蛋白尿は腎臓関係だが、腎臓データの検査結果はなしなので大丈夫そう。2.血糖やHbA1cは正常値なので糖尿病の可能性もなし。
問題2.Aさんは膀胱全摘出術および回腸導管造設術を受けることになった。
Aさんへの術前の説明で正しいのはどれか。
1.「浴槽のお湯に入ることはできません」
2.「水分の摂り過ぎに注意が必要です」
3.「肛門から尿が出ます」
4.「尿意は感じません」
4
尿意は感じない。1.装具をつけて入浴できる。2.尿路感染を防ぐために水分は積極的に摂取し、尿で洗い流す。3.なんでやねん
問題3.Aさんは術後から、これまでにはなかった勃起障害が出現した。Aさんのテストステロン値は13.5pg/mL(50歳代の基準値:4.6~19.6pg/mL)であった。
Aさんの勃起不全の原因で考えられるのはどれか。
1.性ホルモン分泌の低下
2.神経損傷
3.糖尿病
4.喫煙
2
術後に発生したことから神経の損傷が原因であることが考えられる。
株式会社ヒューマンレイズ 大阪市北区西天満4-15-18 プラザ梅新1403
